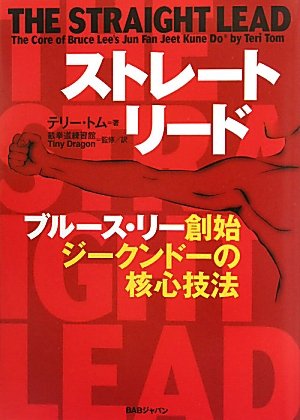映画俳優で、武術家としても評価を得ているブルース・リーが創始した武術「截拳道(Jeet Kune Do/JKD)」。その核心となる技がこの本のタイトルにもなっている「ストレート・リード」と呼ばれるパンチです。
このパンチについて、ブルース・リーの弟子の一人であったテッド・ウォン師夫の弟子であるテリー・トムさんが独自研究によってまとめられています。
截拳道は創始者が道半ばにして亡くなったため、残された後継者によってさまざまな解釈で現在も発展しています。著者は現在知られる截拳道が、ブルース・リー・オリジナルのものではなくなってしまったので、それを修復する作業のファーストステップであると主張しています。
その主張の是非については、すでに創始者本人がこの世の人ではないため、正直なんとも言えません。ただ、「截拳道はなんでもありの寄せ集め武術」的なものではなく、時間をかけて検証され、構築されたシステム・技術が存在するのだということを明らかにしていることは興味深いです。もちろん、日本では格闘技雑誌などで再三特集されているので、多くの武術関係者が認識していることだとは思いますが。
さて、その技術的な分析です。テッド・ウォン師夫はブルース・リーの最晩年の技術を継承しており(いわゆるファイナル・ステージ)、それを保存していく義務があると主張されています。もしそれが本当であるならば、ブルース・リーは最晩年には中国武術の技術体系をすべて捨ててしまったことになると思います。それくらい、この書籍はフェンシングとボクシングの技術に焦点を絞ったものになっています。その根拠はテッド・ウォン師夫が直接ブルース・リーから教授されたものに加えて、最新のブルース・リーのメモと、彼の蔵書の本人のマーキング内容にあるようです。
しかし、この考証には重大な部分が抜け落ちていると私は考えます。彼がそれ以前に習得していた中国武術の体の使い方をボクシングやフェンシングの戦術や体術にどう反映しているか、「截」はもともとは中国の攔截を元に発展したはずなのに、その技術体系に関する記述がない、という点です。線や面などの動きを使って「截」を実現する中国武術的な技術に触れず、離れたところからポイントを狙い合う多分に西洋的な武術に完全に様変わりをしてしまっているのです。これを洗練した、と解釈する人もいるでしょうけど、中国武術の発達の歴史を考えれば逆行ととらえる人もいると思います。
この書籍によれば「ブルース・リーはファイナルステージで詠春拳を捨ててしまった」そうですが、それは実用的でないと気づいたからだそうです。これが本当だとしたら、それはちょっと短絡的に過ぎると私は思います。だとしたら、詠春拳はアメリカであんなに普及しなかったでしょう。逆に修行が足りないのを、術のせいにしている、と言われてもしかたがありません(私は決して、そう思っての発言ではないとは思います。兄弟子に書いた手紙で、「詠春でさえ、畳の上の水練だ」みたいなことを書いていましたけど、全部を否定しているわけではありません)。
基本、ブルース・リーが詠春拳から截拳道に大きくシフトしたのは、1964年の戦いでブルース・リーが背を向けて逃げる相手を詠春拳の技術ではとらえきれなくて、倒すのに数分かかったからだといいます。でも、私はこの話を少年時代に聞いて以来、未だに違和感があります。彼はそれまでその技術で数多くの対戦相手を葬ってきたわけです。たった一回そういうことがあっただけで、「こりゃ全部ダメだ」って思うでしょうか? ※
だいいち、背中を向けて逃げる相手を追う技術? 護身のためならそのまま戦いを終えて安全なところに退避すれば良いし、どうしても戦いたければ(?)走って追っかけるだけですよ。詠春拳に限った話ではないです。
彼が詠春拳を捨ててその技術体系をボクシングとフェンシングに置き換えた、という話になると、一定以上中国武術を修行したことがある人なら違和感を覚えるところではないかと思います。なぜなら、最晩年に作られた彼の映画の中にも、中国武術の体の使い方が色濃く見られるからです。一見大げさに、ボクシング的に放たれている彼のパンチでさえ、高度な中国武術の体の使い方を伺わせています。私は、テッド・ウォン師夫の動きはDVDと動画でしか拝見したことがないのですが、根本的な力の生み方に差があるように感じられます。ブルース・リーには中国武術の確固たる基礎が感じられますが、おそらくテッド・ウォン先生にはそれがありません。逆に言えば、テッド・ウォン先生はブルース・リー以上に「ファイナル・ステージ」なる截拳道を突き詰められた実践者といえるのかもしれません。ただ、仮にファイナル・ステージという段階があったとしても、そこに至るまでの過程が違えば、似たような型に見えても、両者は質の異なったものになるであろうことは想像に難くありません。
ジャック・デンプシーのパワー・ラインについては、ブルース・リーもマークしていたようですが、実は私も四半世紀以上も前に大学の図書館から借りたこのデンプシーの著書を写本したので、強い思い入れがあります。しかし、ブルース・リーが長く学んだ詠春拳も、同じ拳の使い方をすることでパワーを増幅しますし、実際にジョーン・リー氏主催のトーナメントで体の大きな師範代を相手に見せたワンインチ・パンチに関しては、体軸の前傾も使わず、詠春拳的な「パワー・ライン」をかなり使っているように見えます。
こんなこともあって、このストレート・リードがなぜその「東洋的な」部分に触れていないのか不思議な気がしました。多分にフェンシング的な長距離砲だけについてのみではなく、ショートパンチについても触れた資料ですので、そこでどうやって彼が威力を増幅していたのかについてはここに出てくるジム・ドリスコル、ジャック・デンプシー、アルド・ナディの論だけでは説明し切れていません。ただ、詠春拳の場合はリードパンチ、リアパンチの区別がほとんど明確ではないので、論理的な結びつけは確かに難しい部分もあるかもしれません。
私は10代の初めに「魂の武器」、中頃に「秘伝截拳道への道」という書籍を入手しています。このとき、彼のメモと実際の彼の動きが必ずしもリンクしていないことに気づきました。彼自身自分の資料に書籍の内容を引用しているけど、彼自身はその通りの姿勢を必ずしもとっていないわけです。このとき私が考えたのは、確かに彼はそういった格闘技の資料を参考にし、自分の技術の向上に役立てたとは思いますけど、決してそのまま採用したわけではなかったのだろう、ということです。
たとえば、今でもはっきり覚えているのは「顎と肩が中途で出会う」(顎を少し下げ、肩を少し上げることで顎を守り、緊張を最小限にする)構えについてです。10代の後半、これを読んで「おお、いいじゃん」と思って自分もやろうとしたのですが、いざ彼の映画や当時公開されていた多数の写真を見て、「ん、リーさん、全然そんな姿勢も取っていなければ、打ち方をしていないじゃない?」ということになってしまいました。死亡遊戯の池漢戴戦でその大げさな表現が見られるくらいでしょうか? まあ、こういった小さな疑問点もその後中国武術を学んだことで少しずつ解消されていくわけですけど、これはあくまでその当時に感じた一例で、彼の資料やメモと、彼が残した資料やパフォーマンス映像は必ずしも一致していないと思うわけです。
なので、この書籍もブルース・リーの後期の考え方を知る資料の一端として、とても役立つものであると思いますが、これがすべてであるとは思いません。演者のフォームを見ていても、ブルース・リーのフォームというより非常に特徴のあるテッド・ウォン師夫のフォームですし、テリー・トムさんはそれを忠実にコピーしている印象があります。やはり、どんな体系であっても、その人の中を通ることによって、さまざまな変化が生じるのは仕方がありません。例えば、私が直接的に知っている武術の例だと、剛柔流空手。同じ先生から指導を受けたはずの各師範の動きは微妙に違います。その下の代になるとさらに差異が発生しています。でも、みなさん同じように、先生に習ったことをそのまま教えている、と自負されているのです。今回はテッド・ウォン師夫系の書籍ですけど、これはダン・イノサント師夫系の伝承についてももちろん言えることだと私は思っています。
※ ブルース・リーが大きく方向転換した理由としてもう一つ、葉問師夫とのトラブルがあるのではないかと言われています。
1965年に香港に帰省したブルース・リーがアメリカの友人、弟子たちに書いた手紙を見れば、当時彼がどれだけ葉問師夫と詠春拳に傾倒していたかが分かります。これは、上記の逃げる相手を仕留めるのに苦労した1964年の話よりあとのことなのです。しかし、この帰省中に、ブルース・リーは葉問師夫に失礼な要求をしてしまったことで、厳しい叱責を受けることになります。日本流に言えば「破門」でしょうか。彼が詠春拳を離れ、独自の武術に向かうきっかけとなったのではないかというもう一つのエピソードです。
その後5年以上を経て彼は香港に戻り、彼の直接的な師匠(葉問師夫の弟子)とスパーリングをしたという逸話があります。すでに亡いその師匠の弟子に当たる人がインタビューでその目撃談を語っていましたが、その師匠はブルース・リーの蹴りに翻弄され、突きがめちゃくちゃになっていた、とのことでした。ブルース・リーの截拳道に否定的な詠春拳サイドの人の証言なので、信憑性はあると思います。自分なりの方法論で高度な「截拳道」で、過去の「詠春拳」を克服したブルース・リーは非常に優れた、努力の人だったのだと思います。その遺志を継承されているテッド・ウォン師夫やダン・イノサント師夫の功績は多大だと思います。それぞれ派閥にはなっているみたいですけど、これってある意味しかたがないと思います。何も截拳道に限ったことではないですから。それぞれの団体や門下の方々の今後の活躍に期待いたします。